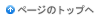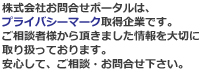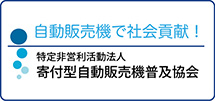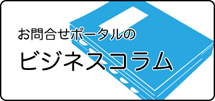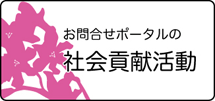- 国内最大級のビジネス比較サイトTOP >
- ビジネスコラム >
- 不具合対策とリコール対応
不具合対策とリコール対応

リコールとは、設計や製造上の過誤などにより製品に欠陥箇所が見つかった場合、法令の規定または製造者や販売者の判断で、製品を無料で回収修理することである。
最近ではアメリカのGM社が、未だ拡大し続けているリコールで揺れまくっている。
今年の2月、過去販売済みの乗用車7車種で点火スイッチの不具合が原因で162万台のリコールを行った。
また、5月にはアメリカの運輸省にリコール対応の遅れを指摘され、GMは罰金3500万ドルを食らうらしい。3500 万ドルは過去最高額で法定の上限だ。
不具合も当然問題だが、GMは10数年前の開発段階から実は不具合を認識していたこと、販売から3年後位にはユーザーからのクレームがあり、すでに社内でもリコールすべきとの声が上がっていたこと、そして何より重大な問題としてはその間に10数人の死亡者が出ていたということだ。死亡者数については、実際はその30倍位という話もある。
つまり、ブレーキに不具合などと、その車に乗せられる方も微妙な事態をGMは10年以上も放置し続け、組織的隠ぺいを続けてきたのではないかとの疑惑が浮上したわけだ。
リコールは、決して悪いことばかりではなく、企業が不具合問題を放置せず、発生した不具合の発表やその不具合への対応を行うからである。
そもそも不具合や欠陥が発生してしまうのは、品質管理の問題やコスト削減・単納期など様々な課題があるが、これを限りなくゼロに持っていく努力はできてもゼロにはできないだろう。
製品トレーサビリティによって、不具合や欠陥が発生した工程や生産箇所、ロット管理、納入先の管理を行うことによって、最小限のリコール対応で済むケースもある。
いつ・どこで・誰が気づけるかが、重要なのだろう。
自動車に関わらず一般製品でも大型のリコールは今後も起こりうるだろうが、リコールは不具合からの事故が発生して初めて対応が始まるケースも少なくない。 リコール製品が場合によっては人体に重大な影響を与え、時には障害が残ったり、最悪死亡事故につながる可能性を考えると、「いや、聞いてないんだけど...リコールされてたの知らなかったんですけど...」では済まされない。 企業や事業者はもっと消費者にきちんとリコール情報が届くよう工夫する必要がある。 と同時に、我々消費者も自分の身を守るため、つぶさにリコール情報のチェックをすることが求められるのではないだろうか。
(タグ:お問合せポータル 廣瀬)