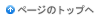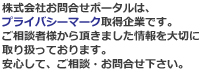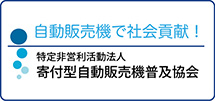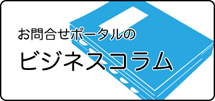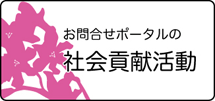- 国内最大級のビジネス比較サイトTOP >
- ビジネスコラム >
- プラットフォーム事業戦略とは?本「プラットフォームの教科書」から学ぶ
プラットフォーム事業戦略とは?本「プラットフォームの教科書」から学ぶ

プラットフォームを展開している事業会社にとっての課題のひとつが「マネタイズ」です。
すなわち、どのようにユーザー数を増やして、どのように利益/キャッシュを生んでいく構造にしていくか?
という戦略の策定と戦術の展開です。
このプラットフォームの戦略策定と事業の展開方法を考察するにあたっては、やはり「プラットフォームとは何なのか?」という基本的な内容を押さえておく必要があります。
そこでお薦めしたい本が、早稲田ビジネススクール教授 根来龍之氏が執筆した本「プラットフォームの教科書」です。
ここでは、本「プラットフォームの教科書」を引用しながら、プラットフォームが発展する原因/要素について考えていきます。
1.プラットフォームの定義とは?
プラットフォームとは何なのか? 非常に平易な形で表現されています。
「お客さんに価値を提供する製品群の土台になるもの。」
(「プラットフォームの教科書」17ページ)
2.プラットフォーム。「2つ」のタイプとは?
プラットフォームは2つのタイプに分かれます。
①基盤型
基盤型プラットフォームとは、補完するサービスとセットで提供することで機能が充実するものを指します。
パソコンのOSと各種アプリケーションソフト等が基盤型プラットフォームの例です。
②媒介型
ユーザー間の売買、コミュニケーションなどの情報流通を促進させるものを指します。
商品/サービスの比較サイト、電子マネーの規格などが該当します。
(本「プラットフォームの教科書」46ページ)
自社のプラットフォームがどのようなタイプに属しているのか?
これを明確にすることで、ユーザーならびにそれに対する提供価値も定義しやすくなります。
3.プラットフォーム事業、プラットフォーム提供者が強大になる理由とは?
プラットフォーマー(プラットフォーム事業者、プラットフォーム提供者)が強大になる理由を押さえることで、自社の戦略、戦術の過不足を判断しやすくなります。
根来教授は、本「プラットフォームの教科書」(7ページ)の中で強大になる理由として4つ列挙しています。
①レイヤー構造
②ネットワーク効果
③エコシステム
④アマチュアエコノミー
次章から①レイヤー構造、③エコシステムの二つを取り上げて説明します。
4.プラットフォームを構成するレイヤー構造の進展。「3つ」の状態とは?
3.では、プラットフォーマーが強大になる理由を4つ記述しました。
ここではそのひとつである①レイヤー構造を取り上げます。
レイヤー構造は、バリューチェーンと対比することで理解が進みます。
バリューチェーンとは、提供者が生産物を製造する過程の上流から下流までをコントロールすることを基本としています。
すなわち、提供者側の視点です。
一方で、レイヤーとは、消費者がサービスを利用するにあたって、提供者ならびに提供者が提携するサービスを「組み合わせ」で選択できる環境を指します。
すなわち、利用者側の視点です。
さて、このレイヤー構造が拡大するということは、プラットフォーマーの影響力が拡大しているということは理解しやすいはずです。
では、レイヤー構造が拡大する、進展するというのはどのような状態なのでしょうか?
大きく3つの状態があります。
①階層が増える。
②各階層が独立化する。
③階層の組み合わせの自由度が増す。
(本「プラットフォームの教科書」42ページ)
5.プラットフォームで展開するエコシステム。配慮する内容とは?
プラットフォーマーが強大になる理由をもう一つ説明します。
エコシステムとは、自社が提供する製品、サービスと提携する他社の製品、サービスの組み合わせで実現する「提供価値」のことです。
このエコシステムを展開するにあたって、配慮する重要なポイントがあります。
それは、「他社にオープンにする範囲」を定義することです。
どの程度まで「補完製品」を「受け入れるか?」を決定することです。
この部分を定義することで、プラットフォームのエコシステムの範囲ならびに協業するサービス、事業会社が明確になります。
昨今、短期間のうちに飛躍的に成長したプラットフォーム提供企業が話題になる事が多いです。
そのため、プラットフォーム戦略に取り組む、または検討する事業会社が増えてきています。
プラットフォーム戦略に取り組む際には、自社が取り組むプラットフォーム戦略はどのタイプで、どのように拡大させていくか、明確に意識して取り組む必要があります。
プラットフォーム戦略に興味がある方は、今回紹介した本「プラットフォームの教科書」を手に取ってみてください。
|
当社/ランドスケイプは、データベース統合ツール「uSonar」を提供しています。 |
執筆者

株式会社ランドスケイプ
ランドスケイプは、日本最大の企業および消費者データベースを駆使したデータベースマーケティングで顧客開拓・育成を支援するコンサルティング会社です。 |
|
このコラムに関連するお問合せポータルカテゴリー
(タグ:株式会社ランドスケイプ)